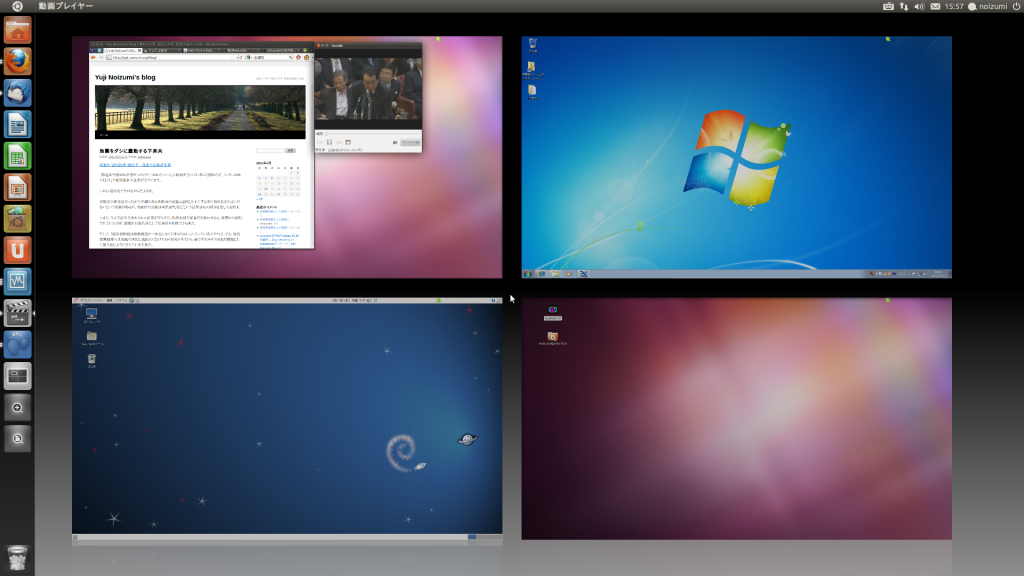libva1とか、ATI のビデオカードの動画再生支援が標準で入るようになった Ubuntu 11.04だが、残念ながら、 xvba-va-driver の依存関係が破損していて入らない。
まず、ソースを取ってくる。
noizumi@purplecat:~/src$ apt-get source xvba-va-driver
パッケージリストを読み込んでいます… 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています… 完了
‘xvba-va-driver’ の代わりに ‘xvba-video’ をソースパッケージとして選出しています
注意: ‘xvba-video’ パッケージは以下の場所の ‘Svn’ バージョン制御システムで保守されています:
svn://svn.debian.org/svn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk
119 kB のソースアーカイブを取得する必要があります。
取得:1 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (dsc) [1,951 B]
取得:2 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (tar) [114 kB]
取得:3 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (diff) [3,044 B]
119 kB を 0秒 で取得しました (265 kB/s)
gpgv: 2010年12月22日 17時46分06秒 JSTにRSA鍵ID 90CBD8E4で施された署名
gpgv: 署名を検査できません: 公開鍵が見つかりません
dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./xvba-video_0.7.7-1.dsc
dpkg-source: info: extracting xvba-video in xvba-video-0.7.7
dpkg-source: info: unpacking xvba-video_0.7.7.orig.tar.gz
dpkg-source: info: unpacking xvba-video_0.7.7-1.debian.tar.gz
依存関係で、fglrx-driverという名前のパッケージは無いので、fglrxに修正する。
noizumi@purplecat:~/src$ vi xvba-video-0.7.7/debian/control
Source: xvba-video
Section: non-free/libs
Priority: optional
Homepage: http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/
Maintainer: Fglrx packaging team <pkg-fglrx-devel@lists.alioth.debian.org>
Uploaders: Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>
Build-Depends: debhelper (>= 7), libva-dev, libgl1-mesa-dev
Standards-Version: 3.9.1
Vcs-Svn: svn://svn.debian.org/svn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk
Vcs-Browser: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk/
XS-Autobuild: yesPackage: xvba-va-driver
Architecture: i386 amd64
Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}, fglrx-driver(>= 1:10-9), libva1
Description: XvBA-based backend for VA API (AMD fglrx implementation)
X-Video Bitstream Acceleration (XvBA), designed by AMD for its ATI/AMD Radeon
GPU, is a future extension of the X video extension (Xv) for the X Window
System on Linux operating-systems. XvBA API allows video programs to offload
portions of the video decoding process to the GPU video-hardware. Currently,
the portions designed to be offloaded by XvBA onto the GPU are motion
compensation (mo comp) and inverse discrete cosine transform (iDCT), and VLD
(Variable-Length Decoding) for MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264) and VC-1 encoded
video.
.
This driver only works with the proprietary fglrx driver from AMD.
noizumi@purplecat:~/src$ cd xvba-video-0.7.7/
noizumi@purplecat:~/src/xvba-video-0.7.7$ dpkg-buildpackage -d
dpkg-buildpackage: export CFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export CPPFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor):
dpkg-buildpackage: export CXXFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export FFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export LDFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -Wl,-Bsymbolic-functions
dpkg-buildpackage: source package xvba-video
dpkg-buildpackage: source version 0.7.7-1
dpkg-buildpackage: source changed by Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>
dpkg-buildpackage: host architecture i386
dpkg-source –before-build xvba-video-0.7.7
fakeroot debian/rules clean
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean
dpkg-source -b xvba-video-0.7.7
dpkg-source: info: using source format 3.0 (quilt)'../xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb’ にパッケージ `xvba-va-driver’ を構築しています。
dpkg-source: info: building xvba-video using existing ./xvba-video_0.7.7.orig.tar.gz
dpkg-source: info: building xvba-video in xvba-video_0.7.7-1.debian.tar.gz
dpkg-source: info: building xvba-video in xvba-video_0.7.7-1.dsc
debian/rules build
dh_testdir
dh_testdir
touch build-stamp
fakeroot debian/rules binary
dh_testdir
dh_testdir
touch build-stamp
dh_testdir
dh_testroot
dh_prep
dh_install "x86/xvba_drv_video.so" "usr/lib/va/drivers/"
dh_testdir
dh_testroot
dh_installchangelogs NEWS
dh_installdocs
dh_install
dh_link
dh_compress
dh_fixperms
dh_strip
dh_installdeb
dh_shlibdeps
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb:
signfile xvba-video_0.7.7-1.dsc
gpg: “Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>”をとばします: 秘密鍵が得られません
gpg: [stdin]: clearsign failed: 秘密鍵が得られません
dpkg-genchanges >../xvba-video_0.7.7-1_i386.changes
dpkg-genchanges: including full source code in upload
dpkg-source –after-build xvba-video-0.7.7
dpkg-buildpackage: full upload (original source is included)
dpkg-buildpackage: warning: Failed to sign .dsc and .changes file
これで、インストール可能な xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb ができあがるので、
noizumi@purplecat:~/src$ sudo dpkg -i xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb
[sudo] password for noizumi:
未選択パッケージ xvba-va-driver を選択しています。
(データベースを読み込んでいます … 現在 140154 個のファイルとディレクトリがインストールされています。)
(xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb から) xvba-va-driver を展開しています…
xvba-va-driver (0.7.7-1) を設定しています …
動作確認
noizumi@purplecat:~/src$ vainfo
libva: libva version 0.31.1
Xlib: extension “XFree86-DRI” missing on display “:0.0”.
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/dri/fglrx_drv_video.so
Segmentation fault
という事で、依存破損を修正してインストールしても、ダメ。
元々入れてたここのモジュールだと、vainfo で segmentation fault する事は無いが、mplayer-vaapi や vlc --ffmpeg-hw で再生できないので、根本的なところで異常となってるのかもしれない。
こういう部分を追っかけようと思うとかなり気合いを入れないといけないので、修正を待とう(^^;